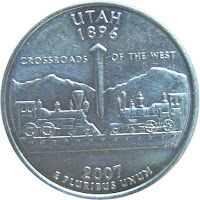この間Cさんに借りていたプレッシャー・ウォッシャーを返しながら雑談になって、
「※パンプキン・カービングをした事はある?」
と、聞かれたので、
「ない」
と、答えたら、
「一度もパンプキン・カービングをしたことないなら、ぜひ一度は体験しなくっちゃ。
火曜日の午前中にあなたの家に行くから、一緒にファーム・マーケットにパンプキンを買いに行きましょう。」
と、言うことになった。
(↑カービングする前のパンプキン)
※パンプキン・カービング:かぼちゃをくりぬいてハロウィンのジャック・オ・ランタンを作ること。
最近は、伝統的なジャック・オ・ランタンのパターンだけでなく、アニメのキャラクターやディズニープリンセスや自分の好きな図柄を彫る人も多い。
(←上の部分をカットして中をくりぬいたところ①)
ファーム・マーケットで、
「あなたと夫と怪獣の分、3つパンプキンを買ってあげる。
あなたに彫り方を教えてあげるから、夫と怪獣が帰ってきたら彫り方を見せてあげて。」
と、言われて。
「家族で1つでいいですよ~」
と、言ったら
「1人に1つ作らなくちゃいけない。私が材料は買うから心配しないで。」
と、言われた。
(←切り抜いたパターンを貼り付けたところ②)
パンプキン・カービングの手順
①上の部分をカットして、スプーンなどで中のワタや種などをくりぬいて皮の厚さが2cmぐらいになるようにする。
カットした上の部分は蓋になるので取っておく。
②好みの図柄をパンプキンに写す。
(今回はパンプキン・カービングのキットについていたパターンを写しました。
図柄を切り抜かずに、ルレットのような物で図柄の上からなぞる方法もある。)
(←パターンに添って、マーカーで図柄を書き込んだところ②)
③調理用ナイフなどで図柄に添って彫って穴を開けていく。
(←左の写真ではキットについていたツールを使用。
見た目よりも柔らかいので彫刻しやすい。
調理用ナイフやキットについているツールは鋭利なので怪我に注意)
④中にキャンドルを入れた時に、絵柄が浮かび上がるように内側の余分な果肉を削る。
(←キャンドルを灯したところ⑤)
⑤キャンドルを灯して飾る
Cさんと交互に彫りながら作業を進めること約2時間。
初めてのパンプキンランタンが出来ました。
この記事を書いている時点ではまだ夫と怪獣のランタンは出来ていませんが、出来次第ブログにUPする予定です。
(↓今回使ったパンプキン・カービングのキット)